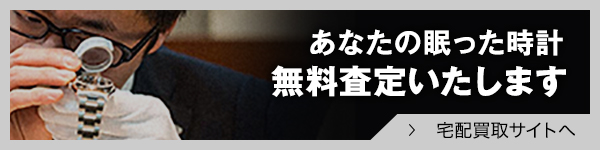2.9.2025
時計の歴史とは?誕生から進化を徹底解説
Komehyo
時刻を把握することは、私たちの日常生活に欠かせません。腕時計やスマートフォンで気軽に時刻を確認できる現代ですが、その背景には数千年にわたる時計の進化があります。
古代の人々が太陽や影を使って時刻を測った古代の日時計から、夜間や天候に左右されない水時計や砂時計、さらに精密さを追求した機械式時計やクォーツ時計を経て、原子時計やスマートウォッチといった高度な時計技術へと発展しています。
本記事では、時計の歴史をわかりやすくたどりながら、人がどのように「時」を正確に刻もうとしてきたのか、その歩みを徹底解説します。
時計とは

時計とは、一定の周期で動く仕組みを基準に「時刻」を示し、必要に応じて「時間の経過」を計測する装置です。
現代では腕時計やスマートウォッチ、スマートフォンなどが身近ですが、その原理は「安定した周期を持つものを基準に時を刻む」という点で共通しています。
古代には太陽の動きや影の長さを利用した日時計、水位の変化で経過時間を測る水時計、砂が一定時間で落ちる砂時計など、自然現象を利用した時計が使われてきました。その後、中世になると歯車やおもりを使った機械式時計が登場し、さらに20世紀には水晶振動子を用いたクォーツ時計が主流になります。現在では、原子の振動を利用した原子時計や、インターネットと連動するスマートウォッチまで、技術は大きく進化しました。
つまり時計は、単なる「時刻を把握する道具」ではなく、人類の科学技術や生活文化の発展と深く結びついて進化してきた存在だと言えます。
自然を利用した時計

時計の歴史の始まりは、人類が自然現象を利用して時刻を把握するようになったところからスタートします。現代のような精密な時計が登場するはるか昔、人々は太陽や水、砂、火といった自然の力を手がかりに、おおよその時刻を把握していました。
こうした自然を利用した時計は、計測精度こそ現代の時計には及びませんが、当時の生活リズムや暦を作るうえで大きな役割を果たしていました。
日時計
太陽の影で時刻を読む「日時計」は、最古の実例が知られるのは紀元前15世紀頃の古代エジプトで、中国・ギリシャ・ローマへ広まりました。板や地面に立てた「グノモン(投影棒)」の影の位置と長さを読むという、仕組みは極めてシンプルです。いっぽうで「太陽が出ないと動かない」「季節と緯度で影が変わる」という根源的な制約を抱えていました。それでも、当時としては一日を通じて時刻を把握できる画期的な発明であり、農作業や宗教儀式、都市の生活リズムを大きく変えました。
水時計
日時計の「日照依存」という弱点を補うために発達したのが、水時計(クレプシドラ/漏刻)です。水を一定の速度で流入・流出させ、その水位の変化で経過時間を読む仕組みで、夜間や屋内でも時を測れます。現存する最古級の実物はエジプト新王国時代(紀元前14世紀)のカルナク出土品で、文献上は紀元前16世紀の記述が見られます。メソポタミアでも水時計は知られ、この技術によって寺院や工房、屋内の公共空間へと用途が広がりました。
古代アテナイの民衆裁判所では、弁論の持ち時間を水時計で管理しました。栓を抜けば水が落ちて審理が進み、法律文の朗読や証人の宣誓のあいだは水を止めて時間に算入しません。訴訟の種類に応じて用いる水量を調整し、持ち時間を配分しました。水が尽きればその時点で時間終了です。ローマでも演説時間の管理に水時計が用いられました。「クレプシドラ」はギリシア語で「水を盗むもの」を意味し、削られていく持ち時間を可視化する装置でもありました。
砂時計
砂時計は、上下のガラス容器を細い管でつなぎ、重力で落ちる砂のほぼ一定の流下速度を利用して時間を計る時計です。誕生時期は定かではありませんが、14世紀頃のヨーロッパで実用が広がったとされます。時代は、いわゆる「大航海時代の前夜」。中世末から近世初頭にかけて地中海だけでなく北海や大西洋沿岸での航海活動が活発化し、沿岸から沖合へと航行範囲が広がり、当直制や航程管理が整備され始めました。光や天候、気温に左右されにくく、揺れる甲板でも扱える「安定した区切り時間」を示す道具が求められ、砂時計はこのニーズに適合します。やがて船鐘と結びついた「30分グラス」は当直のリズムを刻み、航程見積もりや作業サイクルの基準として重宝されました。
この海の要請を後押ししたのが、同時期に発展したガラス製造技術です。ヴェネツィアなどで内面が滑らかな細管や密閉性の高い接合が可能になり、砂の流れが安定。中身も粒度を揃えて乾燥させた粉(卵殻や石灰・大理石粉など)を用いる工夫で、精度と再現性が向上しました。宗教儀式、料理、工房の工程管理など、屋内外の多様な場面にも用途が広がっていきます。
一方で、砂時計は設計時に決めた容量と管径に依存するため、計れるのは「あらかじめ定めた区切り時間」です。湿気対策や密閉で実用性は高まったものの、長時間の通し計測や可変的な配分には向きません。水時計の「揺れ・凍結・蒸発」に弱いという欠点を巧みに回避しつつ、「大航海時代の前夜」に高まった現場ニーズへ応えた道具、それが砂時計でした。
その他の自然時計
自然を利用した時計は、日時計や水時計、砂時計だけではありません。夜間や室内、特定の用途向けにさまざまな工夫が生まれました。例えば、
- ・ろうそく時計
- ・線香時計
- ・オイル時計
などが挙げられます。
ろうそく時計
ろうそく時計は、一定速度で燃えるろうそくの長さを目盛り代わりにした時計です。夜間や室内での時間計測に便利でした。
線香時計
線香時計は、香の燃焼速度を利用した時計です。中国や日本などで広く使われ、特に儀式や宗教行事の時間管理に役立ちました。
オイル時計
オイル時計は、水と油のように比重が異なり混ざらない2種類の液体を封入した時計です。一方の穴から重い水が下へ落ち、もう一方から軽いオイルが上へ逃げる仕組みで、それぞれ色分けされています。
機械式時計の発明と発展

自然の力を利用した時計は便利でしたが、精度や使用環境に限界がありました。そこで中世ヨーロッパでは、歯車やおもりを使った機械式時計が誕生します。これにより時計は大きな転換期を迎え、精度・利便性・耐久性が飛躍的に向上しました。
機械式時計の誕生
13世紀頃のヨーロッパで、「歯車」と「おもり」を動力とし、「ガンギ車」と「フォリオット」で等時性を確保しようとする機械式時計が登場しました。初期の主役は塔に据えられた大掛かりな装置で、文字盤や分針・秒針は一般的ではなく、時を「鐘で告げる」ことが第一目的でした。
機械式時計の最大の功績は、「不定時法」から「定時法」への転換を日常に定着させたことです。季節により昼夜の長さが変わるため一刻の長さも変動する「不定時法」から、1日を24の等しい時間に分ける「定時法」への移行が、塔時計の定時打鐘によって都市生活に広がりました。鐘は市場の開閉、宵の火止め(カーフュー)、労働の始業・終業、礼拝や夜警の当番交代の合図として機能し、都市の経済活動と人びとの行動を同じリズムで動かしました。
15〜16世紀になると、教会・市庁舎・大聖堂の高塔に塔時計が相次いで設置され、この「定時法」の運用基盤が一層強化されました。
振り子時計の登場
16世紀末、ガリレオ・ガリレイは教会の天井から吊るされたランプが揺れる様子を観察し、揺れの幅が変わっても周期はほぼ一定であることに気づきました。この「振り子の等時性」という性質は、精密な計時装置の原理になり得るもので、ガリレオは晩年に振り子を利用した時計の設計に着手します。彼は設計図や試作品の構想を残しましたが、完成を見る前にこの世を去りました。
その着想を受け継ぎ、1656年にオランダの科学者クリスチャン・ホイヘンスが振り子時計を発明します。振り子の等時性を活用することで、それまで1日に10分以上あった誤差を数十秒〜数分程度まで縮めることに成功し、当時としては画期的な精度を実現しました。この進歩は天文学の観測や陸上での測時を大きく改善しましたが、船上のように揺れが大きい環境では精度を保てず、航海用精密時計の実用化は18世紀のクロノメーターを待つことになります。
振り子時計は大型で持ち運びには向きませんでしたが、家庭や公共施設に設置され、正確な時刻を提供する装置として広く使われました。その普及により、商取引や交通、科学研究など、より精密な時間管理が必要な分野が発展していきます。
クロノメーターの登場
18世紀、海上貿易や遠洋探検が活発になるなか、航海士にとって最大の課題のひとつは「正確な経度の測定」でした。経度は基準地点の時刻との差(=時差)から求めるため、船上でも狂いにくい高精度の時計が不可欠でした。これを解決したのが、イギリスの時計師ジョン・ハリソンによる海時計(クロノメーター)です。大型のH1〜H3を経て、1760年代に懐中時計大のH4が実地航海で高精度を示し、海上でも精密な時刻を維持できることを証明しました。これにより、航海中の位置特定は飛躍的に正確になり、貿易・探検・軍事行動に大きく貢献しました。なお、「クロノメーター」は本来、高精度で安定した時刻を示す時計を意味し、現代では公的な精度検定に合格した時計の称号としても使われます。一方、「クロノグラフ」は経過時間を計測するためのストップウォッチ機能を備えた時計であり、両者は目的も機構も異なりますが、クロノグラフが精度検定に合格してクロノメーターと認定される場合もあります。
携帯式時計の登場
時計の技術が進歩すると、小型化の流れが生まれ、持ち運び可能な携帯式時計が誕生します。これが後の懐中時計や腕時計の始まりです。
懐中時計
16世紀頃、ヨーロッパで懐中時計が登場しました。初期の製品は金や銀で装飾された豪華なケースに収められ、主に貴族や富裕層のステータスシンボルとして所有されます。動力源として「ぜんまい(ばね)」が導入され小型化が進みますが、当初は精度・安定性に課題があり、トルクの不均一を補う「フュゼ(鎖引き)」などの機構が工夫されました。
それでも、姿勢差や温度変化、ぜんまいの巻き減りに伴う進み遅れといった根本的な問題は残りました。携帯時計を実用精度へ引き上げるには、調速機構そのものの革新が必要でした。
こうした懐中時計史の中で、もっとも有名な一本として語られるのが、ブレゲの「マリー・アントワネット」(通称「No.160」)です。依頼主はフランス王妃マリー・アントワネット本人ではなく、彼女を崇拝する匿名の人物とされ、当時考え得る最高水準の機構をすべて盛り込むことが求められました。トゥールビヨンこそ発明前のためまだ搭載されていませんが、永久カレンダー、ミニッツリピーター、均時差(エクイション・オブ・タイム)、温度計、パワーリザーブ表示など、主要機構は軒並み盛り込まれています。製作は1783年頃に始まりましたが、設計と製作の複雑さゆえに長期間を要しました。その間、依頼を受けた王妃マリー・アントワネットは1793年に処刑され、時計師アブラアン=ルイ・ブレゲも1823年に死去します。最終的な完成は1827年、ブレゲ没後に工房の弟子によって成し遂げられました。完成したときには、王妃もブレゲ自身もすでにこの世を去っており、時計はまさに数奇な運命を背負った逸品となりました。
なお、2008年にはブレゲが資料と図面に基づく復刻版「No.1160」を一本のみ製作しており、外装・機構ともに当時の仕様を可能な限り忠実に再現した事実上の一点物として扱われています。
ひげぜんまいの発明
17世紀半ばまでの携帯時計は、テンプとガンギ車だけで調速しており、姿勢の変化やぜんまいの巻き具合によって進みや遅れが大きく変動しました。その誤差は1日に数十分に及ぶこともあり、懐中時計は実用品というより装飾品や地位の象徴に近い存在でした。この課題を解決するため、1670年代にオランダの科学者クリスチャン・ホイヘンスが「ひげぜんまい(バランススプリング)」を開発します。これは細いコイル状のぜんまいをテンプの軸に取り付け、往復運動に一定の復元力を与えることで周期を安定させる仕組みで、姿勢やぜんまいの力の変化に左右されにくい調速を可能にしました。
ひげゼンマイの導入により、携帯時計の誤差は日差数分程度にまで改善され、懐中時計は日常生活や商取引、軍事行動など幅広い分野で実用的に使えるようになります。この技術はその後300年以上にわたり機械式時計の基本構造として受け継がれました。発明を巡っては、イギリスのロバート・フックも同時期に同様の機構を考案していたと主張し、優先権を巡る論争が起こります。現在ではホイヘンスが最初に実用化したという説が一般的ですが、両者がほぼ同時期に着想していた可能性も指摘されています。
腕時計
腕時計は16世紀にエリザベス1世にロバート・ダッドリー伯が贈った「腕輪に取り付けた時計(ブレスレット・ウォッチ)」が最古の事例として記録されています。19世紀に入ると貴婦人向けの宝飾的な腕時計が作られ、1868年にはパテック・フィリップがハンガリーの伯爵夫人のために腕時計を製作しました。
同時期、一般には懐中時計が主流でしたが、20世紀初頭に小型化が進み、腕時計は手首で瞬時に確認でき両手も使える実用品として普及します。第一次世界大戦では、兵士の実用需要を背景にハミルトンやブライトリングが軍用腕時計を大量生産し、男性の時計は懐中時計から腕時計へと大きく移行しました。戦後は多くの懐中時計メーカーも腕時計製造へ転換します。
その後は防水性・耐久性・精度の改善が進み、20世紀末には腕時計は日常生活に不可欠なアイテムとして世界中に定着しました。
複雑機構の発展
機械式時計は単に時刻を表示するだけでなく、追加機能(コンプリケーション)を搭載することで進化を続けてきました。中でも、自動巻き機構、トゥールビヨン、永久カレンダーは、精度や利便性、美しさを象徴する代表的な複雑機構として知られています。
自動巻き機構

自動巻きの発想は18世紀に始まり、1770年代には「ペルレ」や「サルトン」が懐中時計で自動巻きの原型を考案しました。
腕時計での実用化は1923年、「ジョン・ハーウッド」が特許を取得したモデルです。リューズを廃して回転ベゼルで時刻を合わせる独創的な設計で、1928年には量産も始まりました。
普及を決定づけたのは1931年の「ロレックス・パーペチュアル」で、360度回転ローターにより効率が飛躍的に向上し、現代の自動巻きの基本形が確立しました。
戦後はさらに進化し、「フェルサ・Bidynator」の両方向巻上げ(1942年)、「IWCペラトン式」(1950年)、「セイコー・マジックレバー」(1959年)などが登場。現在の機械式腕時計にも広く受け継がれています。
トゥールビヨン

18世紀末、フランス生まれの天才時計師アブラハム=ルイ・ブレゲによって考案された機構です。当時の懐中時計は常に垂直に近い姿勢で携帯されるため、重力の影響による姿勢差が精度低下を招いていました。これを補正するため、ブレゲは1801年にフランスで特許を取得し、脱進機やテンプを回転ケージに収めて一定周期で回転させ、重力の影響を平均化する「トゥールビヨン」を開発しました。
当初は軍人や航海士など高精度を求める用途に向けて実用化が試みられましたが、製作は極めて難しく高価であったため、ごく限られた顧客にしか提供されませんでした。ブレゲ自身も生涯でわずか数十個しか製作しておらず、現存する初期のトゥールビヨン懐中時計は世界的に貴重な存在です。
20世紀に入ると、実用性以上に技術と美観の象徴として再評価され、特に1980年代以降の機械式時計復興期には高級ブランド各社がこぞって採用しました。現在では「超高級時計の証」とされ、シングル、ダブル、トリプル軸やフライングトゥールビヨンなど複雑な進化形も登場しています。
有名なエピソードとして、ブレゲがこの機構を発表した際、同時代の時計師からは「実現不可能」と見なされましたが、自らの精緻な技術によって完成させました。その革新性ゆえに、トゥールビヨンは今日に至るまで「時計技術の頂点」を象徴する存在とされています。
永久カレンダー

永久カレンダーは、月ごとの日数やうるう年まで自動計算し、正しい日付表示を維持する複雑機構です。通常のカレンダー機構では30日や31日の月末ごとに手動調整が必要ですが、永久カレンダーは「2100年にうるう年が閏日を持たない」特例を除けば、半永久的に修正不要です。
この発想の原点は18世紀にさかのぼり、天才時計師アブラハム=ルイ・ブレゲが懐中時計に初めて永久カレンダー機構を組み込んだとされています。その後、19世紀を通じて高度な懐中時計に採用され、王侯貴族の間で珍重されました。
腕時計としての永久カレンダーは20世紀に入ってから実用化されます。1925年、スイスのパテック・フィリップが世界初の永久カレンダー腕時計を製作しました。これは元々懐中時計用のムーブメントを小型化して搭載したもので、後に同社はカタログモデルとしても提供を開始。以降、ヴァシュロン・コンスタンタンやオーデマ・ピゲなど、数多くの名門ブランドが追随しました。
永久カレンダーはきわめて複雑な歯車構造を持ち、製作には高い技術と精密な調整が要求されます。その精度と利便性から「高級機械式時計の象徴」とされ、単なる時間を測る道具を越えて「機械仕掛けの芸術品」として愛好家から絶大な支持を集めています。
クォーツ式時計の発明と発展
20世紀後半、時計の歴史を大きく変える技術革新が訪れました。それがクォーツ式時計の登場です。機械式時計がゼンマイと歯車で動作するのに対し、クォーツ式は水晶振動子の規則正しい振動を利用して高精度な時間計測を実現しました。
クォーツ時計の誕生

クォーツ時計は1927年、アメリカのベル研究所で初めて開発されましたが、当初は大型で研究用装置に近く、実用化には至りませんでした。
その後、小型化研究が進むなか、日本のセイコーは東京オリンピック(1964年)の公式計時を通じて高精度化の必要性を痛感し、社運を賭けた開発を推進。10年以上の研究を経て、1969年に世界初の市販クォーツ腕時計アストロンを発表しました。発売当初は自動車並みに高価でしたが、量産化によって急速に普及します。
クォーツ時計の強みは月差数秒の高精度と低コストで、大量生産に適していました。この革新はスイスの機械式時計業界を直撃し、1970〜80年代に多くの企業が倒産・統合に追い込まれるクォーツショックを引き起こしました。
しかし、この危機を契機にスイスメーカーは機械式を「高級品・芸術品」として再定義し、現在の高級市場の礎を築くこととなります。
デジタルウォッチとスマートウォッチ

クォーツ技術の発展は、表示方式にも変化をもたらしました。1970年代には液晶やLEDを使ったデジタルウォッチが登場し、時刻や日付、ストップウォッチ機能などが手軽に表示できるようになります。
さらに21世紀に入ると、時計は単なる時刻表示の道具から多機能デバイスへ進化します。スマートウォッチはBluetoothやWi-Fiでスマートフォンと連携し、通話、通知、健康管理、GPSナビゲーションなど、多彩な機能を搭載するようになります。Apple WatchやGarmin、Samsung Galaxy Watchなどが代表的です。
これらの進化により、時計は単なる「時刻を把握する道具」から、「生活をサポートするウェアラブルデバイス」へと変貌しました。
原子時計の発明と発展

クォーツ時計をさらに上回る精度を実現したのが原子時計です。1955年、イギリス国立物理研究所で開発されたセシウム原子時計が最初の実用化モデルとされ、これにより「時間の定義」そのものが科学的に大きく変わりました。
原子時計の仕組み
原子時計は、原子が特定のエネルギー状態の間で遷移するときに放出する電磁波の振動数を基準として時刻を計測します。 特にセシウム133原子は安定した振動を持ち、1秒はセシウム原子が基底状態の2つの超微細準位間を9,192,631,770回遷移する時間と定義されています。この仕組みにより、原子時計の誤差は数千万年に1秒程度と驚異的な精度を誇ります。
原子時計の用途
原子時計は、その極めて高い精度からさまざまな分野で利用されています。
- ・GPS:衛星に搭載された原子時計が、位置情報の精度を決定
- ・通信ネットワーク:5Gやインターネット通信での正確な同期
- ・科学研究:天文観測や地球物理学での高精度測定
- ・金融取引:ミリ秒単位の取引記録における正確なタイムスタンプ
私たちの日常生活に密接に関わる技術インフラの多くが、原子時計の精度に支えられています。
未来の時計技術
原子時計は現在も進化を続けています。次世代技術として注目されているのが、100億年で1秒の誤差という非常に高い精度を誇る光格子時計です。光格子時計は、レーザー光によって冷却・固定された原子の振動を基準にすることで、さらに高い精度を実現しようとしています。これにより、秒の定義そのものが将来的に光格子時計に基づく形へと変更される可能性もあります。
また、超高精度時計の普及は、地殻変動の観測や相対論的な時間計測、さらには宇宙探査にも新たな可能性を開くと期待されています。
まとめ

時計の歴史は、日時計や水時計といった自然時計から始まり、機械式時計、クォーツ時計、原子時計、そしてスマートウォッチへと進化してきました。その過程で精度や機能は飛躍的に向上し、私たちの生活は常に「正確な時刻」とともに歩んできました。
しかし現代では、時計の役割や価値観は単純な「時刻を正確に測るための道具」から大きく広がっています。携帯可能な時計の使われ方も、ライフスタイルや目的によって多様化しました。
- ・スマホで十分という人:携帯電話やスマートフォンの時計機能で事足りる人は、腕時計を身につけない傾向があります。
- ・実用として腕時計を使う人:仕事や日常生活での時刻確認や機能性を重視し、クォーツ腕時計やスマートウォッチを選ぶ人が増えています。
- ・趣味・ファッションとして腕時計を楽しむ人:機械式時計や宝飾時計など、機能だけでなくデザインやブランドの価値を楽しむ層も根強く存在します。
こうした用途の多様化により、「最新の技術=スタンダード」という時代ではなくなりました。むしろ、用途や好みに応じて、それぞれが自分に合った時計を選ぶ時代になっているのです。
TAGLIST
- A.LANGE&SOHNE
- , AUDEMARS PIGUET
- , Bell&Ross
- , BLANCPAIN
- , Breguet
- , BREITLING
- , BVLGARI
- , CARTIER
- , CASIO
- , CHANEL
- , CHOPARD
- , CITIZEN
- , F.P.JOURNE
- , FRANCK MULLER
- , G-SHOCK
- , Girard-Perregaux
- , Glashütte Original
- , GRAND SEIKO
- , HAMILTON
- , HERMES
- , HUBLOT
- , IWC
- , Jaeger-LeCoultre
- , Lemania
- , Longines
- , MAURICE LACROIX
- , MORITZ GROSSMANN
- , NEXT VINTAGE
- , NOMOS
- , OMEGA
- , ORIS
- , PANERAI
- , PATEK PHILIPPE
- , PIAGET
- , RICHARD MILLE
- , ROLEX
- , SEIKO
- , SINN
- , SWATCH
- , TAG HEUER
- , Timex
- , TISSOT
- , TUDOR
- , Ulysse Nardin
- , VACHERON CONSTANTIN
- , VINTAGE
- , ZENITH
- , その他
- , クォーツ
- , パテックフィリップ
- , ファッション
- , フレデリックコンスタント
- , 人物
- , 時計一般知識
- , 独立時計師
- , 筆記具
- , 革靴
more
-
NEXT ARTICLE
次の記事へ

17.9.2025
オーデマ ピゲはどんな人が買える?維持費・購入方法と主なコレクションを徹底解説

-
PREVIOUS ARTICLE
前の記事へ


25.8.2025
【OMEGA】スピードマスターオートマチック Ref.351050の魅力|プロフェッショナルモデルと徹底比較